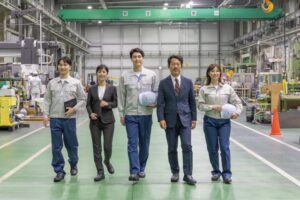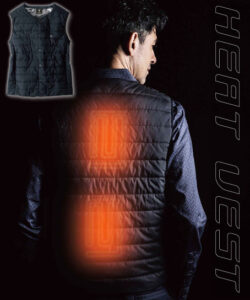- ホーム >
- ユニフォーム制服のお役立ちコラム >
- 作業着 >
- 作業服選びの決定版!撥水と防水の違いを徹底解説~現場のプロが教える失敗しない選び方~
 作業服選びの決定版!撥水と防水の違いを徹底解説~現場のプロが教える失敗しない選び方~
作業服選びの決定版!撥水と防水の違いを徹底解説~現場のプロが教える失敗しない選び方~

目次
撥水と防水、実は全然違う!基本の「き」を知ろう
撥水って何?水をコロコロ弾く魔法のような仕組み
作業服を選ぶとき、「撥水」と「防水」って書いてあるけど、正直どっちがどっちだかよくわからない…なんて経験ありませんか?実はこの2つ、似てるようで全然違うんです!
まず撥水から説明しましょう。撥水って言うのは、文字通り「水を弾く」機能のこと。イメージとしては、車のワックスをかけた後のボンネットに雨が降ったときみたいな感じです。水滴がコロコロ〜って転がって落ちていく、あの現象ですね。
撥水加工された作業服の表面には、特殊なコーティングが施されています。このコーティングが水分子と仲良くしたがらない性質(疎水性)を持っているので、水が生地に染み込む前にペタペタくっつかずに弾かれちゃうんです。
でも注意が必要なのは、撥水はあくまで「弾く」だけということ。長時間雨に打たれたり、水圧がかかったりすると、徐々に染み込んでくることがあります。軽い雨や水しぶき程度なら問題ないけど、完全に水をシャットアウトするものではないんですね。
防水の真実!完全シャットアウトの代償とは
一方、防水は「水を通さない」機能。こちらは撥水よりもワンランク上の性能と考えてもらっていいでしょう。
防水加工の作業服は、生地そのものが水分子を通さない構造になっています。代表的なのは、生地の裏面にウレタンコーティングや塩化ビニール系のフィルムを貼り付けたもの。これにより、水が生地を貫通することを物理的に防いでいるんです。
「それなら防水の方が絶対いいじゃん!」って思うかもしれませんが、ちょっと待って。防水にも弱点があるんです。
最大のデメリットは「蒸れ」です。水を完全にシャットアウトする構造ということは、内側から出る汗や水蒸気も外に逃がしにくいということ。特に夏場の作業や動きの多い仕事だと、サウナスーツ状態になってしまうことも…。
また、防水加工された作業服は一般的に重くなりがちで、動きにくさを感じることもあります。さらに、コーティング部分が剥がれやすく、経年劣化しやすいのも気になるポイントです。
透湿性能が作業服選びのキモ!蒸れない秘密を大公開
透湿って聞いたことある?汗っかきさん必見の機能
ここで登場するのが「透湿」という機能。これ、知ってる人と知らない人で作業服選びの満足度が全然変わってくる重要なポイントなんです。
透湿とは、「水蒸気を通す」機能のこと。つまり、外からの雨は防ぎつつ、内側の汗や湿気は外に逃がしてくれる、まさに理想的な機能です。
仕組みはちょっと複雑なんですが、簡単に言うと、水の分子(液体)は通さないけど、水蒸気の分子(気体)は通すような極小の穴が生地に空いているイメージ。この穴のサイズが絶妙で、雨粒は大きすぎて通れないけど、汗が蒸発した水蒸気は小さいので通り抜けられるんです。
透湿性能は「g/㎡/24hr」という単位で表されます。これは、1平方メートルあたり24時間でどれだけの水蒸気を透過するかを示しています。一般的に、8,000g/㎡/24hr以上あれば実用的、15,000g/㎡/24hr以上あれば高性能と言われています。



ゴアテックスが最強と言われる理由を分解してみた
透湿防水素材の代名詞と言えば「ゴアテックス」。アウトドア用品から作業服まで、幅広く使われているこの素材、なぜこんなに評価が高いのでしょうか?
ゴアテックスの秘密は、「PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)」という素材にあります。これを極薄のフィルム状にして、1インチ四方に約90億個という超微細な穴を空けているんです。この穴のサイズが絶妙で、水滴の約2万分の1、水蒸気分子の約700倍という大きさ。
つまり、雨粒は物理的に通れないけど、水蒸気はスルスル通り抜けられる構造になっているわけです。まさに理論上最強の透湿防水素材と言えるでしょう。
しかも、ゴアテックスの透湿性能は驚異的で、一般的なゴアテックス製品で15,000〜25,000g/㎡/24hrという数値を誇ります。これは、汗っかきの人でも快適に過ごせるレベルです。
ただし、ゴアテックスにも注意点があります。まず、価格が高いこと。本格的なゴアテックス素材を使った作業服は、一般的な作業服の3〜5倍の価格になることも珍しくありません。
また、透湿機能を発揮するためには、生地の外側が濡れすぎないことが重要です。表面がびしょ濡れになると、水の膜ができて水蒸気の透過が妨げられることがあるんです。



耐水圧と防風性能で現場の厳しさに立ち向かえ!
耐水圧の数値、どれくらいあれば安心?実測データで検証
作業服選びで意外と見落とされがちなのが「耐水圧」。これは、どれだけの水圧に耐えられるかを示す数値で、mmH2O(ミリメートル水柱)という単位で表されます。
具体的に言うと、耐水圧10,000mmというのは、1cm四方の生地の上に10メートルの高さまで水を積んでも漏れない、ということを意味しています。
では、実際の作業現場ではどれくらいの耐水圧が必要なのでしょうか?
・小雨:約300mm
・普通の雨:約2,000mm
・大雨:約10,000mm
・嵐クラス:約20,000mm以上
さらに、作業中の動きや圧力も考慮する必要があります。例えば、膝をついて作業したり、背中に圧力がかかったりする場面では、静止状態の何倍もの圧力がかかることがあります。
一般的に、屋外作業なら最低でも10,000mm、できれば15,000mm以上の耐水圧があると安心です。特に建設現場や農作業など、激しい雨の中でも作業を続ける可能性がある職種なら、20,000mm以上を目安にするといいでしょう。
防風機能で体感温度が激変!冬場の作業効率UP術
意外と軽視されがちなのが「防風」機能。でも実は、これが作業効率に与える影響は思っている以上に大きいんです。
風速1m/秒につき、体感温度は約1度下がると言われています。つまり、気温10度で風速10m/秒の環境では、体感温度は0度になってしまうということ。これでは作業どころではありませんよね。
防風機能のある作業服は、風の侵入を防ぐことで保温効果を大幅にアップさせます。同じ気温でも、防風機能があるかないかで作業効率が全然変わってくるんです。
防風性能は「CFM(立方フィート毎分)」という単位で表されることが多く、数値が小さいほど防風性能が高いということになります。一般的に、CFM5以下なら実用的、CFM1以下なら高性能と考えていいでしょう。
また、防風機能と透湿機能を両立させるのはなかなか難しく、ここでも技術の差が出てきます。安価な防風素材は透湿性が犠牲になりがちで、結果的に蒸れやすくなってしまうことも。



シームレス加工の威力とプリント剥離の落とし穴
シームレス技術で弱点を克服!縫い目から水が入らない工夫
どんなに優秀な防水・透湿素材を使っても、縫い目から水が侵入してしまっては意味がありません。そこで重要になってくるのが「シームレス加工」(シームシーリング)です。
一般的な作業服では、生地同士を糸で縫い合わせていますが、この縫い目は針穴があいているため、どうしても水が侵入しやすい弱点になってしまいます。
シームレス加工では、縫い目の裏側に特殊なテープを熱圧着で貼り付けることで、針穴を完全に塞いでしまいます。このテープ自体も防水性と透湿性を持っているため、縫い目部分でも本来の性能を維持できるんです。
シームレス加工にはいくつかの種類があります:
・完全シームレス:すべての縫い目にシーリング処理を施したもの。最高レベルの防水性を誇りますが、価格も高くなります。
・重要部位シームレス:肩や背中など、特に水が侵入しやすい部分のみにシーリング処理を施したもの。コストパフォーマンスに優れています。
・部分シームレス:袖口や裾など、限定的な部分のみの処理。エントリーモデルに多く見られます。
撥水生地とプリントの剥離要因を知って長持ちさせるコツ
撥水生地を使った作業服でよくあるトラブルが、プリントや刺繍の剥がれです。これは撥水生地特有の性質が関係しているんです。
撥水生地は表面に特殊なコーティングが施されているため、通常のプリント方法だと密着性が悪くなってしまいます。特に以下のような要因で剥離が起こりやすくなります:
・熱による劣化:高温での洗濯や乾燥により、撥水コーティングとプリントの接着力が弱くなる
・摩擦による剥がれ:作業中の擦れや引っかかりにより、プリント部分に物理的な力がかかる
・化学薬品の影響:洗剤や漂白剤、作業現場の化学物質により、接着層が劣化する
・経年劣化:紫外線や温度変化により、材料そのものが劣化する
これらの問題を避けるためには:
1. 適切な加工方法の選択:撥水生地には専用のプリント方法(転写プリントや特殊インク)を使用する
2. プリント位置の工夫:摩擦の少ない部位にデザインを配置する
3. 適切なメンテナンス:洗濯時は裏返しにして、低温設定で洗う
4. 定期的な撥水処理:撥水性能が落ちてきたら、市販の撥水スプレーで補修する
現場のプロが教える!用途別作業服選びの最終チェックポイント
屋外作業vs屋内作業、シーン別ベストチョイス
ここまで様々な機能について説明してきましたが、結局のところ、どの機能を重視すべきかは作業環境によって大きく変わります。

屋外作業(建設・土木・造園など)の場合
・耐水圧:15,000mm以上
・透湿性:10,000g/㎡/24hr以上
・防風性:CFM3以下
・シームレス加工:重要部位は必須
・推奨:ゴアテックスまたは同等の高機能素材
天候に左右される屋外作業では、やはり防水・透湿・防風のトリプル機能が重要。特に長時間の作業が予想される場合は、透湿性能を重視しましょう。
屋内作業(工場・倉庫など)の場合
・撥水性:あれば十分
・透湿性:5,000g/㎡/24hr程度
・防風性:不要
・価格重視:コストパフォーマンスを優先
・推奨:撥水加工のポリエステル混紡素材
屋内作業では過度な防水性能は不要。むしろ軽量性や動きやすさ、洗いやすさを重視した方が実用的です。
季節作業(農業・林業など)の場合
・春夏:透湿性重視(15,000g/㎡/24hr以上)
・秋冬:防風性重視(CFM2以下)
・年間通して:耐久性とコスパのバランス
・推奨:季節ごとに使い分け可能なシステム
季節によって必要な機能が変わる職種では、インナーとアウターを組み合わせるシステムが効果的です。
コスパ最強!長期使用を前提とした投資の考え方
作業服は消耗品とはいえ、できるだけ長く使いたいもの。初期投資は高くても、長期的に見ればお得になることも多いんです。
高機能素材の投資価値を計算してみましょう
一般的な作業服(5,000円):
– 寿命:約6ヶ月
– 年間コスト:10,000円
– 快適性:★★☆
高機能作業服(20,000円):
– 寿命:約2年
– 年間コスト:10,000円
– 快適性:★★★
この例では年間コストは同じですが、快適性や作業効率を考慮すると、高機能作業服の方が圧倒的にお得です。
さらに、以下のような隠れたコストも考慮すべきです:
健康面のコスト
・蒸れによる肌トラブル
・体温調節不良による体調不良
・ストレスによる作業効率低下
時間的コスト
・頻繁な買い替えにかかる時間
・不快感による作業中断
・洗濯・メンテナンスの手間
これらを総合的に判断すると、用途に合った高機能作業服への投資は十分に価値があると言えるでしょう。
まとめ
撥水と防水の違いから始まって、透湿、防風、耐水圧、シームレス加工、そしてプリント剥離の問題まで、作業服選びには本当にたくさんのポイントがあります。
でも一番大切なのは、自分の作業環境と必要な機能を正しく把握すること。オーバースペックでお金を無駄にすることもなければ、必要な機能が不足して後悔することもありません。
この記事で紹介した知識を活用して、あなたにとって最適な作業服を見つけてください。きっと今まで以上に快適で効率的な作業ができるはずです!